「思ったより売上が伸びない」「経費が予想以上にかかっている」――そんな経験はありませんか。
中小企業や個人事業主にとって、資金や時間の余裕は限られています。だからこそ、計画と実績のズレを早く把握し、手を打つことが欠かせません。
そこで役立つのが予実管理です。予算(計画)と実績(結果)を比べ、原因を分析して改善につなげるこの方法は、難しい仕組みや高価なシステムがなくても始められます。
本記事では、予実管理の基本から成果を出すための運用ポイントまで、実践しやすい形でご紹介します。
数字が会社を救う!予実管理の基本と効果
「予実管理」という言葉を聞くと、難しくて専門的な印象を受けるかもしれません。
ですが、実はとてもシンプルで、経営を安定させるうえで欠かせない考え方です。
予実管理とは、「あらかじめ立てた計画(予算)」と「実際の結果(実績)」を比べ、その差の理由を探ることです。
イメージとしては、旅先で地図を見ながら「今どこにいて、目的地までどれくらいかかるか」を確認するようなものです。
たとえば、旅行で「2日目は観光地Aに行く」と計画しても、当日、天候や交通事情で到着が遅れたら予定を見直します。。
経営も同じで、予定通りに進んでいるかを定期的にチェックし、必要があればすぐに方向を修正することが大切です。
中小企業・個人事業主にこそ効果的な理由
大企業であれば、多少計画がズレても、潤沢な資金や人員の余裕で立て直すことができます。
しかし、中小企業や個人事業主の場合はそうはいきません。大企業に比べて資金や時間に限りがあるため、一度の判断ミスが経営に大きなダメージを与えることもあります。
たとえば、予定外の経費が重なって資金繰りが急に苦しくなった経験はないでしょうか。
予実管理をしていれば、早い段階で「経費が予定を上回っている」と気づき、削減や営業強化といった対策をすぐに打てます。
これは、車でいう「事故を防ぐブレーキとハンドル」を持っているようなものです。
予実管理で得られる3つのメリット
1つ目は、お金の流れが「見える化」されることです。
予算と実績を並べてみると、どの項目にどれだけお金を使っているのかが一目でわかります。
たとえば「広告費が予定の1.5倍になっている」など、数字が具体的に見えることで、感覚ではなく事実に基づいた判断ができます。
2つ目は、ムダな支出を減らせることです。
数字で比較することで「本当に必要な支出なのか?」を冷静に判断できます。
たとえば、なんとなく続けている広告や、ほとんど使っていないサブスクリプションサービスなど、毎月の固定費を見直すきっかけになります。
こうして削減できたお金を、売上アップにつながる投資や必要な備品の購入に回せば、事業の成長にもつながります。
3つ目は、経営判断が早くなることです。
予実管理をしていないと、決算や確定申告の時期になって初めて「思ったより利益が少ない」と気づくこともあります。
その時には手遅れになるケースも少なくありません。
毎月、予算と実績を比べる習慣があれば、「このままでは赤字になる」という兆候を早く察知し、その場で改善策を打てます。
予実管理の簡単な始め方
予実管理は、この不安を解消し、数字を味方につけるためのシンプルな方法です。
難しそうに聞こえますが、特別なソフトも専門知識も不要です。
エクセルやノート、さらには手帳でも始められます。
ちょっとした習慣にするだけで、ムダな支出を減らし、利益を守り、経営の判断スピードが格段に上がります。ここでは、初心者でも今日から取り組める予実管理の始め方を、3つのステップでご紹介します。
年間・月間の「予算」を立てる
まずは年間のゴールを決めることから始めましょう。
ゴールとは、今年1年間で達成したい売上や利益の目標額です。
最初はとりあえずでもよいのでざっくり年間目標額を決めてみましょう。
たとえば「年間売上1,200万円、利益200万円」を目標にするとします。
そして、ここで終わりにせず、年間目標を毎月の目標に落とし込むことが大切です。
年間の数字を12で割れば、1か月あたりの目安が出ます。
売上なら月100万円、利益なら月約16万円という具合です。
年間の数字だけでは「まだ時間がある」と思ってしまいがちですが、毎月の目標があれば、遅れに気づきやすくなります。
さらに、経費も大まかに見積もります。
家賃や水道光熱費、広告費などの固定費と、材料費や外注費など売上に応じて増減する変動費を分けて考えます。
こうして作った年間予算と月別予算が、予実管理の土台となり、毎月の数字チェックの基準になります。
こちらの記事で、必要利益から目標となる売上高を計算する方法を解説しています。
宜しければチェックしてみてください。
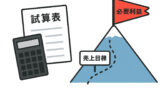
実績の集計は毎月行う
予算を立てたら、次にやるべきは毎月の実績記録です。
これを継続することで、予算との差を早く把握でき、手遅れになる前に対策を打てます。
実績の記録方法は大きく2つあります。
1つ目は、ご自身で記帳や集計を行う方法です。
会計ソフト、エクセル、ノートに「日付・内容・金額」を記入し、売上と経費を毎月合計します。
売上は請求書やレジの集計、経費は領収書やカード明細をもとにすれば、特別なソフトがなくても始められます。
2つ目は、税理士に依頼して毎月の試算表を作ってもらう方法です。
記帳や集計の手間が省けるだけでなく、数字の見方や改善のアドバイスも受けられるため、より効果的に予実管理を運用できます。
どちらの方法を選ぶにしても、「毎月」集計することが何より重要です。
数か月分まとめて集計しようとすると、数字のズレや原因を正確に把握できなくなります。
「月末に必ず記録」、「毎月税理士から試算表を受け取る」など、タイミングを固定して習慣化することが成功のカギです。
予算と実績を比較するチェックリスト
記録ができたら、次は予算と実績を比べる作業です。
ここで重要なのは、「差額がプラスかマイナスか」だけを見て終わらせないこと。
本当に大事なのは、その差が生まれた理由を探ることです。
理由を見つける際には、次のようなチェックリストが役立ちます。
- 売上は予算より増えているか、減っているか?
- 増減の理由は「新規顧客」か「リピート顧客」か?
- 経費は予算通りか?増えている項目は何か?
- 増えた経費は将来の売上につながる投資か?
- このままのペースで年間目標を達成できるか?
たとえば、売上が予算より10万円多かった場合でも、その原因が「単価アップ」なのか「一時的な大口案件」なのかで、次の打ち手は変わります。
また、経費が増えていても、それが広告投資で来月以降の売上アップにつながるなら、問題どころか成長のための投資と考えられます。
数字はあくまで“結果”であり、その背景には必ず理由があります。
増減の理由を掘り下げてこそ、予実管理は経営の羅針盤として機能します。
予実管理は、最初から完璧を目指す必要はありません。
重要なのは、「予算を決める」→「実績を毎月記録する」→「予算と比べて原因を探る」という流れを継続することです。
このサイクルを毎月回すことで、数字を見る力がつき、経営判断のスピードも格段に上がります。
成果を出すための運用ポイント
予実管理は、ただ数字を比べるだけの作業ではありません。
せっかく記録しても、使い方を間違えると効果は半減します。
ここでは、予実管理を経営の武器に変えるための4つのポイントをご紹介します。

適切な予算(目標)を設定する
予算は「無理な理想」でも「安全すぎる数字」でもなく、現実的かつ挑戦できる目標に設定することが大切です。
たとえば、前年の売上が1,000万円なら、まずは1,050万~1,100万円のように少し背伸びした数字を目指すと、モチベーションが保ちやすくなります。
また、年間目標だけでなく、必ず月ごとの目標に落とし込みましょう。
年間だけだと遅れに気づくのが遅くなりますが、毎月の目標があれば「今どの位置にいるのか」が明確になります。
PDCAが大切
予実管理は、**計画(Plan)→実行(Do)→確認(Check)→改善(Action)**のサイクルで回すことが重要です。
このサイクルを毎月回せば、小さな改善を積み重ねて大きな成果につなげられます。
たとえば、広告費を増やして売上がどう変化したかを確認し、効果があれば継続、なければ見直す。
このように、数字を見て「次にどう動くか」を決めるのがPDCAの本質です。
細かい差異は気にしない
予算と実績を比べると、数千円単位のズレは必ず出てきます。
しかし、その小さな差異にこだわりすぎると、本当に注目すべき大きな変化を見落としてしまいます。
たとえば、売上が予算より5,000円少ない場合よりも、広告費が予算より10万円増えている場合のほうが、経営に与える影響は大きいものです。
数字を見るときは、重要な差とそうでない差を見極める視点を持ちましょう。
状況が変わったら固執せず予算を見直す
予算は一度決めたら絶対に動かしてはいけない、というものではありません。
市場環境や取引先の状況が大きく変わったときには、柔軟に見直すことも必要です。
たとえば、想定外の大型受注があった場合や、逆に大口取引が終了した場合は、その後の予算も修正したほうが現実に合った管理ができます。
予算に縛られるのではなく、状況に合わせて使いこなすことが、予実管理を成果につなげるコツです。
予実管理は、ただの数字合わせではなく、経営を改善するための行動指針です。
「適切な目標設定」「毎月のPDCA」「重要な差異に集中」「柔軟な見直し」を意識すれば、数字が経営の強力な味方になります。
まとめ
予実管理は、数字で現状を把握し、改善の方向を見極めるための経営ツールです。
重要なのは、適切な目標を立てる→毎月実績を記録する→原因を分析して行動に移すという流れを継続すること。
年間だけでなく月ごとの目標を設定し、PDCAを回し、経営を見直すことが成果につながります。
特別なシステムは不要で、エクセルやノートでも始められます。
毎月の試算表を税理士に依頼すれば、精度とスピードも向上します。
まずは今月から、小さくても予実管理を始めてみませんか。
自社に合った方法を知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。



