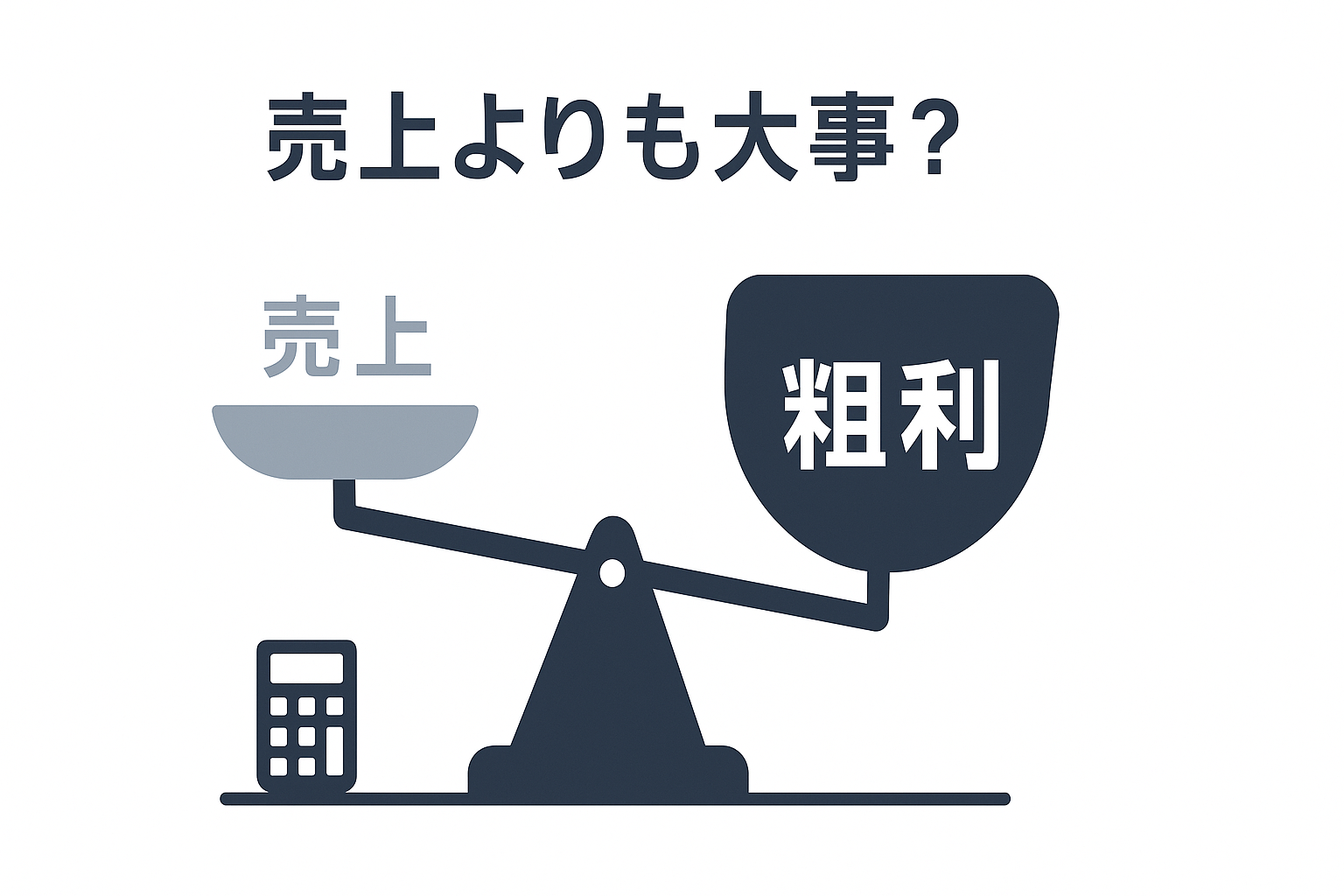はじめに:売上が増えているのに、お金が残らない?
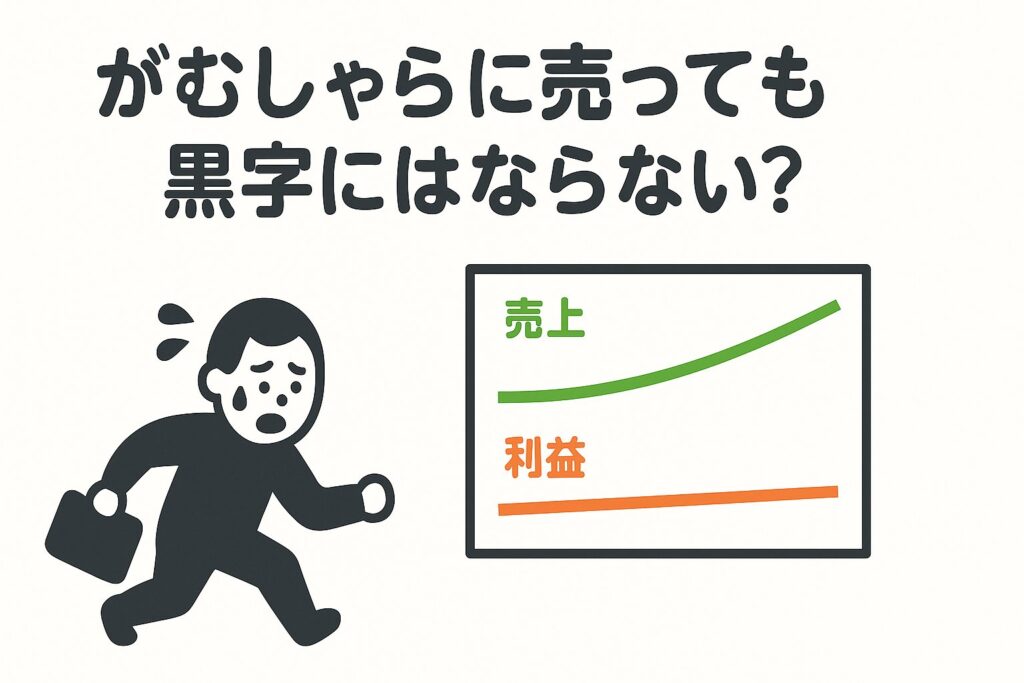
「売上は右肩上がりなんですけど、なぜか資金繰りが苦しいんですよね…」
これは私たち税理士が、よく聞く経営者の悩みの一つです。
努力して売上を伸ばしているのに、利益が思ったよりも残らない。そんな経験はありませんか?
実は、その答えは「売上」ではなく「粗利」に隠されています。
本記事では、「粗利とは何か?」「なぜ粗利を見なければならないのか?」「粗利から会社の強み・弱みをどう読み解くのか?」をわかりやすく解説します。
数字が苦手な経営者の方でも、今日から実践できる内容になっています。どうぞ最後までご覧ください。
「売上」にばかり目が行くと利益が残らない?
「売上=会社の成績」と考えていませんか?
もちろん売上は重要な数字です。しかし、それだけを追いかけてしまうと、気づかぬうちに利益が削られていた…ということも珍しくありません。
売上が大きくても、仕入や外注費、人件費などのコストがそれ以上にかかっていれば、結果的に「利益が残らない会社」になってしまいます。
とくに、次のような経営スタイルの方は要注意です。
- 安く売って数を稼ごうとする(薄利多売)
- 値上げができず、価格競争に巻き込まれている
- 外注費や仕入価格の上昇に気づかず対応が遅れている
こうしたケースでは、どれだけ売上を上げても“お金が残らない体質”に陥ります。
だからこそ、「売上」よりも「粗利(=会社に残る利益の源泉)」を見る必要があるのです。
粗利とは何か? 会社にとっての“筋肉量”を測る数字
まず、粗利とは何かを確認しておきましょう。

▶ 粗利(売上総利益)=売上 - 仕入・外注費などの原価
たとえば、100万円の商品を販売して、仕入や外注費が60万円かかった場合、粗利は「40万円」になります。
この40万円から、家賃・人件費・広告費などの固定費を差し引いて、最終的に利益が出るかどうかが決まります。
つまり粗利は、「自社がどれだけ“商品で”稼げているか」を示す非常に重要な指標なのです。
言い換えれば、粗利とは会社の筋肉量。売上は見た目の大きさにすぎませんが、粗利がしっかりあれば、経営は持続可能になります。
粗利が高い会社・低い会社の特徴とリスク
粗利の高い会社と、低い会社では、経営スタイルやリスクも大きく異なります。
▶ 粗利が多い会社の特徴
- 単価が高く、価格競争に巻き込まれにくい
- 専門性・技術力が強みになっている
- 社内での内製化が進んでいる
- お客様が「価格より価値」で選んでくれている
こうした会社は、仮に売上が少し落ちても粗利がしっかり残るため、利益を確保しやすい構造になっています。
▶ 粗利が少ない会社の特徴
- 単価が安く、数で稼ぐビジネス(薄利多売)
- 価格競争が激しい業界(卸売・建設下請け等)
- 外注・仕入比率が高く、コントロールが難しい
- 自社の価値よりも「価格」で選ばれている
こうした会社は、売上が伸びていても利益が薄く、原価や外注費のわずかな変動が大きな痛手になります。
粗利率が下がれば下がるほど、「売っても売っても資金繰りが苦しい」状態に陥ります。
粗利を見るための3つの実践ステップ
ここからは、実際にどうやって粗利を「経営の判断材料」として活用していくか、3つのステップで解説します。
ステップ①:売上と仕入・外注費を月ごとに記録する
まずは、売上だけでなく「仕入」「外注費」も毎月把握しましょう。
クラウド会計やExcelを活用すれば、簡単に管理できます。
数字が苦手な経営者ほど、以下のような「ざっくり表」から始めるのがおすすめです。
| 月 | 売上 | 仕入+外注費 | 粗利 | 粗利率 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2,000,000円 | 1,200,000円 | 800,000円 | 40% |
| 2月 | 1,800,000円 | 1,100,000円 | 700,000円 | 38.9% |
数字はシンプルで構いません。まず「見る」ことが大事です。
ステップ②:粗利率の変化を追う
粗利率(粗利 ÷ 売上)は、会社の「体質」を表す指標です。
毎月の粗利率を記録することで、次のような変化に気づけます。
- 原価が上がっているのに、売値を据え置いていた
- 高粗利の商品が減り、低粗利の仕事ばかりが増えていた
- 外注先の値上げがじわじわ響いていた
粗利率が少しでも下がったときは、なぜそうなったのか、必ず原因を探る習慣をつけましょう。
ステップ③:粗利から経営の打ち手を考える
粗利を見て終わりではありません。粗利の情報を活用して、「次の一手」を考えることが大切です。
たとえば…
- 粗利率が高い商品を強化する
- 粗利の低い取引を減らす or 値上げ交渉する
- 外注を減らして内製化する
- 単価を上げるための付加価値を追加する
売上アップよりも、粗利率の改善の方が短期的に効果が出やすいケースも多々あります。
実例でわかる!粗利が語る会社の“強み”と“弱み”
ここでは、実際にあった2つの事例をご紹介します。
事例①:価格交渉に成功した製造業A社
A社は、長年付き合っている得意先からの値下げ要請を断り切れず、粗利率が年々低下していました。
月次で粗利を可視化したところ、実は“付き合いで受けていた仕事”ほど利益が薄いと判明。
そこで経営者は、粗利率の高い製品に注力し、赤字ギリギリの案件は思い切って断る方針に切り替えました。
結果、売上は一時的に減少しましたが、利益はむしろ増加。資金繰りも安定しました。
事例②:外注比率の高さに気づいたサービス業B社
B社はIT系の受託開発をしており、案件ごとにフリーランスへ外注していました。
月次で粗利を見たところ、売上の約70%が外注費で消えていると判明。
そこで、自社内に若手を育成する体制を作り、外注依存を減らす戦略へシフト。
2年後には粗利率が10%以上改善し、利益率も安定しました。
まとめ|売上より「粗利」。会社の未来はここから変わる
売上が伸びているのに会社にお金が残らない…。
そんなときは、「売上」ではなく「粗利」に目を向けるタイミングかもしれません。
粗利は、会社のビジネスモデルそのものを映し出す数字です。
・何を売って
・誰に売って
・どのくらい利益が残っているのか
これらを月次で確認するだけでも、経営の精度は大きく上がります。
数字に強くなる必要はありません。
「粗利」というたった1つの数字に注目するだけで、会社の強み・弱み、そして未来が見えてきます。
ご自身の会社の粗利を知りたい、改善したいといった方はぜひササキ税理士事務所までお問い合わせください。